老人ホームに入居を考えている方の中には、
「費用がどのくらいかかるのか心配…」
「年金だけで支払えるかどうか不安…」
と、お悩みの方もいるのではないでしょうか。老人ホームに入るには高額な費用がかかると思っている方も多いですが、公的施設と民間施設でかかる費用に差があり、公的施設なら比較的リーズナブルに利用できます。
本記事では、老人ホームへの入居検討にあたり、費用が払えるかどうか心配している方に向けて、有料老人ホームの平均利用額をはじめ、費用の内訳、費用捻出ができなくなった場合の対処法などを解説します。
有料老人ホームの平均利用額は?平均寿命までのシミュレーションも紹介

老人ホームとは、介護施設のうち「高齢者に対する介護サービスを備えている施設全般」を指し、その中に有料老人ホームも含まれます。また、老人ホームは以下の2つに分類できます。
| 公的施設 |
ケアハウス
特別養護老人ホームなど |
| 民間施設 |
介護付き有料老人ホーム
住宅型有料老人ホーム
サービス付き高齢者向け住宅
グループホームなど |
「公的施設」は、社会福祉法人や地方自治体により運営されており、比較的リーズナブルに利用できます。対して、民間企業により運営される「民間施設」は、事業者によって費用が異なり、中には入居に高額な費用がかかる高級な老人ホームもあります。
厚生労働省の資料(参考:サービス付き高齢者向け住宅等の月額利用料金)によると、有料老人ホームの月々の利用料金総額の平均は18万9,982円となっています。この利用料金総額には、「家賃+共益費+基本サービス相当費+食費+水道・光熱費」が含まれています。このデータを使って、生涯に渡って老人ホームを利用した場合に「最終的にどれくらいの費用が必要になるのか」を試算してみます。
厚生労働省の「令和5年簡易生命表」によると、75歳時点の平均余命は、男性で約12年、女性で約15年です(参考:厚生労働省|令和5年簡易生命表)。75歳で有料老人ホームに入居し、平均寿命まで暮らしたと仮定して計算すると、次のようになります。
男性(12年間滞在):
18万9,982円 × 12か月 × 12年 = 2,735万4,208円
女性(15年間滞在):
18万9,982円 × 12か月 × 15年 = 3,419万6,760円
老人ホームを終の棲家として選択した場合、入居から亡くなるまでまでに必要な費用は、およそ2,700〜3,400万円台と見込むことができます。ただし、これはあくまで平均から計算しただけの単純な試算なので、もっと安くすむ可能性もありますし、逆に要支援・要介護の状態となり、介護サービスを利用した場合はもっと高くなる可能性もあります。では、有料老人ホームに入居すると、他にどのような費用がかかるのか、内訳について詳しく解説していきます。
有料の老人ホームの費用内訳は?相場はいくら?

有料老人ホームの利用料金の主な内訳は、家賃、共益費、基本サービス相当費、食費、介護保険料や医療費、その他の雑費です。株式会社野村総合研究所が平成27年に公表した「高齢者向け住まいが果たしている機能・役割等に関する実態調査」を参照しながら、それぞれの内訳を見ていきましょう。
老人ホームの費用①:家賃
月額利用料金のうち、介護付き有料老人ホームの家賃の平均は7万5,601円。住宅型有料老人ホームの平均は3万8,689円という結果でした。この数字は前払い金を設けていない施設のみの金額であり、前払い金を設けている場合の介護付き有料老人ホームの平均は月5万9,868円。住宅型有料老人ホームの平均は4万408円です。ちなみに前払い金とは、入居時に支払うお金のことで、入居一時金(後述)とも呼ばれています。入居時にまとめて支払うため、前払い金が多いと月々の利用料金を安く抑えられます。
老人ホームの費用②:共益費
介護付き有料老人ホームの共益費相当額の平均は5万3,355円。住宅型有料老人ホームは2万1,094円です。介護付き有料老人ホームの「共益費相当額」とは、マンションの共益費に類似した費用です。建物の維持、共用部分の水道光熱費や管理のために必要なお金以外にも、施設職員の人件費が含まれることがあります。介護付き有料老人ホームのほうが住宅型有料老人ホームよりも高額なのは、「人件費の負担が大きい」という理由もあるのではないでしょうか。
老人ホームの費用③:基本サービス費相当額
介護付き有料老人ホームの「基本サービス費相当額」の平均は1万2,573円。住宅型有料老人ホームの平均費用は5,832円です(介護保険1割負担は除く)。
基本サービス費相当額には、一般的に生活支援やスタッフによる健康管理、受ける介護サービスに応じた費用が含まれますが、入居者の要支援・要介護の認定内容によっても異なります。介護保険法で指定された基準を満たしている介護付き高齢者ホーム「特定施設(特定施設入居者生活介護)」に入居した場合、要介護度によって以下のように月額の自己負担額が決められています。
| 要介護度 |
1割負担 |
2割負担 |
3割負担 |
| 要支援1 |
5,460円 |
10,920円 |
16,380円 |
| 要支援2 |
9,330円 |
18,660円 |
27,990円 |
| 要介護1 |
16,140円 |
32,280円 |
48,420円 |
| 要介護2 |
18,120円 |
36,240円 |
54,360円 |
| 要介護3 |
20,220円 |
40,440円 |
60,660円 |
| 要介護4 |
22,140円 |
44,280円 |
66,420円 |
| 要介護5 |
24,210円 |
48,420円 |
72,630円 |
※出典URL:厚生労働省「介護報酬の算定構造」
ただし居住地域によって、自己負担額は異なる可能性があります。
老人ホームの費用④:水道・光熱費、食費
介護付き有料老人ホームの平均の水道・光熱費は6,500円、住宅型有料老人ホームは5,397円という結果でしたが、施設や運営会社によっては、水道光熱費が管理費に含まれているケースもあります。大半の介護付き有料老人ホームでは、固定費として毎月一定額を支払うパターンが多いようです。また、介護付き有料老人ホームの食費の平均(3食を30日間提供した場合)は4万9,611円、住宅型有料老人ホームの平均は3万8,943円でしたが、食費には食材費とは別に厨房維持管理費が含まれることもあります。
老人ホームの費用⑤:介護保険料や医療費、その他の雑費
上記の費用以外に介護保険料の負担額や医療費をはじめ、消耗品、嗜好品、洋服代といった雑費はすべて自己負担です。個人差はあるものの、月3〜5万円はプラスで見込んでおくとよいでしょう。なお、消耗品にはティッシュ、石鹸、歯ブラシ、歯磨き粉、シャンプーなどがあり、入居者や家族が用意する場合もあれば、施設が補充した後、費用を請求されることもあります。オムツを使用する場合は、別途オムツ代もかかります。理容師・美容師の定期訪問や、自由参加の有料イベント(陶芸やヨガなど)に参加する際も費用が発生するでしょう。
老人ホームの「入居一時金」とは?費用の平均額はいくら?

入居一時金には「家賃の前払い」という意味合いがあり、この前払い金は、終身にわたって居住することを想定して支払うお金です。老人ホームでの契約は、「居室や共用スペースの利用などを終身にわたり利用できる権利を取得する」という「利用権方式」が一般的です。そのため、有料老人ホームに入居する場合は、「利用権を前もって取得する」という意味合いで、原則前払い金を支払うケースが多いでしょう。前払い金は、「①想定居住期間における家賃」+「②想定居住期間を超えた期間に備えた家賃(将来の家賃負担)」から構成されており、想定居住期間を超えずに退去する場合は、残りの金額を返金してもらえます。
先述した株式会社野村総合研究所の「高齢者向け住まいが果たしている機能・役割等に関する実態調査」によると、介護付き有料老人ホームの平均の前払い金は392万2,494円で最大値は6,000万円。住宅型有料老人ホームの平均は51万5,316円で最大値は5,320万円です。入居一時金が安い場合は月額利用料の設定額を上げているケースが多いので、入居一時金の額だけではなく、総額で判断する必要があるでしょう。また、入居一時金がない老人ホームに入居する場合は、入居時に「敷金」が別途必要となり、月々の利用料金も高くなるのが一般的です。このように相場はピンからキリまであります。入居前にしっかり調べておきましょう。
| 以下のような老人ホームや介護施設のポータルサイトでは、検索する際に入居費などの「費用」で絞込検索することができます。自分の予算感でどのような施設があるのか、費用の相場感を調べるの活用できます。
|
老人ホーム費用の支払い方法
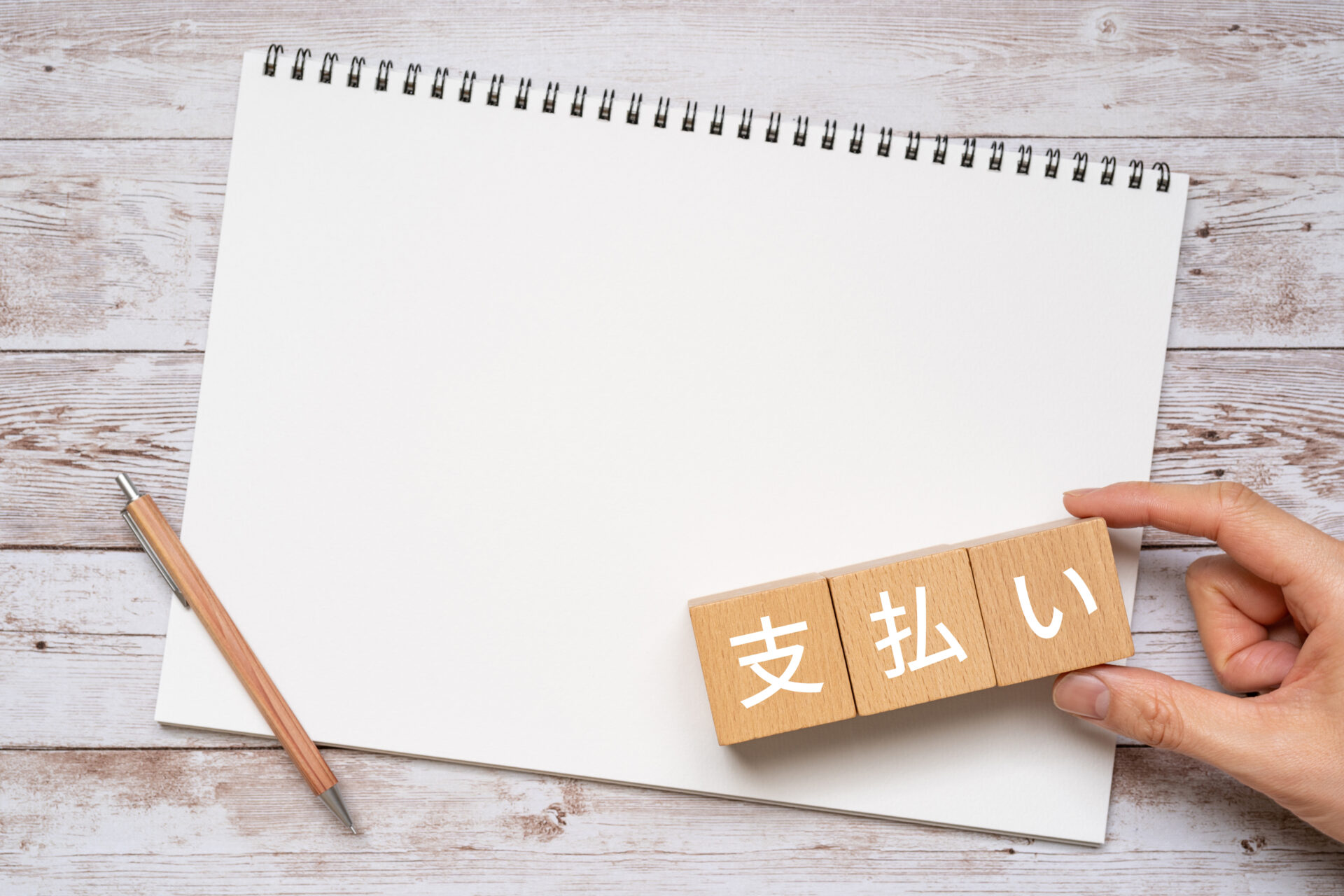
老人ホームの費用には3つの支払い方法があります。
1つ目は「一時金方式(全額前払い方式)」です。入居時にまとまった費用を一括で支払うことで、月々の家賃や管理費などの支払いが無くなります。長期的に利用する予定がある場合に、総費用を抑えられる可能性があります。
2つ目は「一部前払い方式(一部月払い方式)」です。想定する居住期間の家賃の一部を入居時に支払い、残りの費用を月々分割して支払う方式で、初期負担を抑えながら月々の負担も調整しやすいのが特徴です。
3つ目は「月払い方式」とよび、入居時に前払いをせず、毎月定額の利用料を支払っていく方式です。短期間の利用を予定している方や手元資金に不安がある方に適しています。
施設によっては、これらの支払い方式の中から希望に応じて選択できる場合もあります。以下のようなメリット・デメリットを理解したうえで、支払方法を選択しましょう。
| 支払い方式 |
メリット |
デメリット |
| 一時金方式
(全額前払い) |
・毎月の負担が軽くなる
・長期入居で総額が安くなることがある |
・高額な初期費用が必要
・途中退去時の返還額が少ないことがある |
| 一部前払い方式
(一部月払い方式) |
・初期費用と月額のバランスが取れている
・柔軟な支払い設計が可能 |
・前払い分が無駄になるリスクがある
・仕組みが複雑なことが多い |
|
月払い方式
|
・初期費用が抑えられる
・短期利用の場合の無駄が少ない |
・長期入居では総額が割高になることがある
・月々の負担が大きくなる |
なお、毎月の支払いが発生する方式を選択し、入居後になんらかの原因で費用負担ができなくなった場合、入居の継続ができなくなる恐れがあります。
親が老人ホームに入居する際の費用負担を把握する
親の老人ホーム入居の費用を、子どもが負担するケースも少なくありません。子どもが負担する費用の額は、親の年金収入や貯蓄、不動産などの資産状況によって異なるります。事前にしっかり相談・確認しておくことが大切です。また、兄弟姉妹がいる場合は、どのように費用を分担するか、早めに話し合っておくことで、のちのトラブルを防ぐことができます。なお、一定の条件を満たすことで、費用負担を軽減できる控除や公的制度もあります。これについては、次の段落で詳しく解説します。
老人ホームの費用に対して使える控除や負担を軽くする制度

老人ホームの費用は控除の対象になる
まずは、老人ホームの費用負担を軽減できる控除を紹介します。老人ホームの費用は、条件を満たせば医療費控除などの税制優遇措置の対象になります。本人だけでなく、親や配偶者、扶養親族の入居費用も対象となる場合があります。控除を受けるには確定申告が必要です。
医療費控除
医療費控除とは、1年間に自分や家族のために支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告によって、当該超過分を所得から差し引いて税金を軽減できる制度です。老人ホームの入居にかかる費用のうち、一定の費用は「医療費控除」の対象になります。控除の対象となる項目は、以下のように介護施設の種類によって異なります。
| 介護保険施設の種類 |
医療費控除の対象となる費用 |
医療費控除の対象外の費用 |
| 特別養護老人ホーム |
・介護費、食費、居住費などの施設サービス費(支払った額の1/2に相当する金額)
・おむつ代(要おむつ使用証明書) |
・日常生活費
・特別なサービス費 |
| 介護老人保健施設 |
・介護費、食費、居住費などの施設サービス費(支払った全額)
・おむつ代(要おむつ使用証明書) |
| 介護医療院 |
| 介護療養型医療施設 |
参考:国税庁|No.1125 医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価
医療費控除の対象にならない項目として、「日常生活費」や「特別なサービス費」があります。「日常生活費」とは、理美容代や、施設サービスで提供されるもので、日常生活で必要になるものを指し、入居者に負担させるのが適当な項目のことです。「特別なサービス費」とは、レクリエーションの参加費や個室の利用料(診療や治療を受けるためにやむを得ず支払う場合は対象となる)などを指します。なお、上記以外の施設(ケアハウスやグループホームなど)の場合、施設サービス費などは医療費控除の対象になりません
扶養控除(親・その他親族)
扶養控除とは、納税者が一定の要件を満たす親族を扶養している場合に、所得税や住民税の課税所得を減らすことができる制度です。老人ホームに入居している親なども、条件を全て満たせば扶養控除の対象となることがあります。扶養親族に該当する人の主な条件は次の通りです(12月31日時点で全て満たす必要あり)。
- 6親等内の血族および3親等内の姻族または里子や市町村長から養護を委託された老人
- 納税者と同一生計(老人ホーム入居中でも仕送りなどで生計が共通なら対象になる)
- 年間の合計所得金額が48万円以下
- 青色事業専従者として通年で一度も給与支払いを受けていない
- 白色事業専従者でない
扶養控除の金額は、扶養親族の区分によって異なります。「一般の控除対象扶養親族」「特定扶養親族」「老人扶養親族」の3つがあり、それぞれ年齢要件によって区分されています。区分ごとの年齢要件・控除金額は、以下の表をご覧ください。
扶養控除額(2024年時点)
| 扶養親族の区分 |
年齢要件 |
控除額(所得税) |
| 一般の控除対象扶養親族 |
16歳以上
(その年の12月31日現在) |
38万円 |
| 特定扶養親族 |
19歳以上23歳未満
(その年の12月31日現在) |
63万円 |
| 老人扶養親族
(同居老親等以外の者:自分または配偶者の父母・祖父母などで同居していない方。老人ホームなどの入居者も含む) |
70歳以上
(その年の12月31日現在) |
48万円 |
| 老人扶養親族
(同居老親等:自分または配偶者の父母・祖父母などで同居している方) |
58万円 |
※その他詳しい要件については、国税庁の公式サイトをご確認ください。
参考:国税庁|No.1180 扶養控除
配偶者控除
配偶者控除とは、納税者の配偶者が一定の所得以下の場合に、所得税の課税所得を減らすことができる制度です。配偶者控除の対象となる配偶者は、以下の条件を満たす必要があります。
- 納税者と配偶者が民法上の婚姻関係にあること
- 納税者と同一生計であること
- 配偶者のその年の合計所得金額が48万円以下であること
- 青色事業専従者として通年で一度も給与支払いを受けていないこと
- 白色事業専従者でないこと
上記の条件を満たした方は「一般の控除対象配偶者」となり、同条件で70歳以上(その年の12月31日現在)の方は「老人控除対象配偶者」となります。配偶者控除の控除額は、以下のように配偶者の年齢と納税者本人の合計所得金額によって異なります。
| 納税者本人の合計所得金額 |
一般の控除対象配偶者 |
老人控除対象配偶者
※70歳以上(その年の12月31日現在) |
| 900万円以下 |
38万円 |
48万円 |
| 900万円超950万円以下 |
26万円 |
32万円 |
| 950万円超1,000万円以下 |
13万円 |
16万円 |
参考:国税庁|No.1191 配偶者控除
障害者控除(本人・配偶者・扶養親族)
障害者控除は、納税者本人またはその扶養親族が一定の障害者に該当する場合に、所得税の課税所得から所定の金額を控除できる制度です。障害者の範囲は広く、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方、特定の認定を受けた方などが含まれます。詳細な対象者の範囲については、国税庁の公式サイトをご参照ください。 (参考:国税庁|No.1160 障害者控除)障害者に該当する方は27万円、特別障害者に該当する方は40万円が控除されます。
老人ホームでの費用負担を軽減できる制度
ここからは、老人ホームの費用負担を軽減するために知っておきたい制度について解説します。
高額介護サービス費支給制度
高額介護サービス費支給制度は、介護保険サービスの自己負担額が一定の上限を超えた場合に、超過分が払い戻される制度です。たとえば、以下のような介護保険サービスが該当します。
居宅サービス(自宅生活で利用する介護サービス)
- 訪問介護(買い物や身の回りのサポート)
- 通所介護(デイサービスなど)
- 短期入所(ショートステイなど)
介護施設サービス(施設入居中に利用する介護サービス)
施設の居住費や食費などは介護保険サービスではないので、高額介護サービス費支給制度の対象にはなりません。自己負担の上限額は、所得や課税状況に応じて設定されています。以下は2024年8月時点の上限額です。
| 所得区分 |
世帯の上限額(月額) |
| 生活保護受給者 |
1万5,000円(世帯) |
| 市町村民税非課税 |
2万4,600円(世帯) |
| 市町村民税非課税(前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下) |
2万4,600円(世帯)
1万5,000円(個人) |
| 市町村民税課税 課税所得380万円(年収約770万円)未満 |
4万4,400円(世帯) |
| 課税所得380万円(年収約770万円)〜690万円(年収約1,160万円)未満の |
9万3,000円(世帯) |
| 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 |
14万100円(世帯) |
(参考:厚生労働省)
申請方法や詳細については、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口にお問い合わせください。
特定入所者介護サービス制度
特定入所者介護サービス費(補足給付)制度は、介護保険施設や短期入所サービスを利用する際の食費・居住費の自己負担を、所得や資産状況に応じて軽減する制度です。特別養護老人ホームや介護老人保健施設、ショートステイなどの介護保険施設における居住費やサービスが軽減の対象になります。
この制度では、利用者の所得・資産状況・市町村民税の課税状況などに応じて、第1~第3段階に区分されます。判定された段階が低いほど、自己負担も軽くなる仕組みです。利用者の預貯金額にも基準が設けられており、一定額以下でなければ制度を利用できない場合があるため注意が必要です。制度を利用するには、市区町村に申請し「介護保険負担限度額認定証」の交付を受ける必要があります。
年金で足りる?費用を抑えて入れる老人ホームは?(特別養護老人ホーム・軽費老人ホームなど)
 2024年度の年金支給額は、国民年金(老齢基礎年金)が満額で月額6万8,000円、夫婦二人の老齢基礎年金を含む厚生年金(老齢厚生年金)は、平均的な収入で40年間就業した場合で月額約23万483円となっています。(参考:日本年金機構|令和6年4月分からの年金額等について)年金をまだ受給していない場合は、「ねんきんネット」や「ねんきん定期便」などを活用して、自身の見込み受給額を確認しておくと安心です。親族が老人ホームに入居する場合も、必要となる負担額を把握するために、事前に確認しておきましょう。
2024年度の年金支給額は、国民年金(老齢基礎年金)が満額で月額6万8,000円、夫婦二人の老齢基礎年金を含む厚生年金(老齢厚生年金)は、平均的な収入で40年間就業した場合で月額約23万483円となっています。(参考:日本年金機構|令和6年4月分からの年金額等について)年金をまだ受給していない場合は、「ねんきんネット」や「ねんきん定期便」などを活用して、自身の見込み受給額を確認しておくと安心です。親族が老人ホームに入居する場合も、必要となる負担額を把握するために、事前に確認しておきましょう。
先ほど述べたように、老人ホームは大きく社会福祉法人や医療法人、地方自治体が運営する「公的施設」と、民間企業が運営する「民間施設」に分かれます。一般的に民間の有料老人ホームは費用が高く、運営会社によっても差が生じます。その点、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院といった公的施設は、民間施設よりも費用を安く抑えられるでしょう。たとえば特別養護老人ホームは、基本的に要介護度3以上の高齢者が入居できる施設で入居一時金は不要です。
前年度の個人収入(年金)や、住環境の違いなどによって自己負担額は変わりますが、たとえば要介護5の人が多床室(他の入居者と共同生活する部屋のタイプ)を利用した場合の月額利用料はおよそ10万円(施設サービス費の1割・居住費・食費・日常生活費)です。個室の場合は、費用が上乗せされます。ほかにも、軽費老人ホーム(A型、B型、都市型軽費老人ホーム、ケアハウス)は入居一時金がかかるケースはあるものの、比較的安い月額利用料で入居できます。収入額に応じて負担額は月4〜15万円と幅があります。国民年金だけでは入居できる施設が限られますが、厚生年金を受給する場合は、毎月の費用を年金のみでまかなえるケースも増えるため、選択肢の幅も広がります。
生活保護でも老人ホームに入れる?利用額は0円!?
仮に受給している年金が少なく、生活に困窮している場合は、条件次第で生活保護を申請できます。生活保護が認められれば、家賃扶助や生活扶助などを受けられるため、有料老人ホームの費用をまかなえる可能性があるでしょう。扶助の金額は収入、世帯の人数、居住している市区町村などによって変わりますが、家賃扶助と生活扶助を合わせて月8〜13万円が多いようです(詳細は居住地域の市区町村にお問い合わせください)。ただし有料老人ホームは民間施設なので、生活保護者を受け入れていないケースもあります。一方、特別養護老人ホームや軽費老人ホームは公的施設なので生活保護を受けていても申請可能ですし、介護扶助の対象となり、要介護度に応じた限度額以内であれば無料で利用できるでしょう。
毎月の利用料金が負担に!?老人ホームの費用が払えない場合は?
有料老人ホームへの入居後に収入の状況が変わり、「毎月の利用額を支払えなくなった…」ということは誰にでも起こる可能性があります。
たとえば、有料老人ホームの費用として老後資金を貯めていたにもかかわらず、家族が別の用途で使い込むケースがあるかもしれません。仮に月額利用料を支払えなくなっても、即退去を迫られることはまずありません。多くの施設では、1〜2カ月ほどの猶予期間を設けています。また入居者本人が月額利用料を支払えなくなった場合は、身元引受人(連帯保証人)が代わりに支払うことになります。ちなみに有料老人ホームへの入居時に身元保証が求められ、契約時には身元引受人が必要になりますが、身寄りがいないケースもあるでしょう。その場合、保証会社などの法人(株式会社、一般社団法人やNPO法人など)と契約して身元保証人制度を利用することも可能です。本人の財産管理や、費用の支払い代行に対応している法人もあります。
身元保証人も月額利用料を支払えない場合は再び退去勧告を受けますが、保証会社などの法人であれば、預託金に基づいて費用を支払うので安心感があるでしょう。「どうしても費用を支払えない」と分かったら、その時点で施設のケアマネジャーに相談し、今より安価な施設を紹介してもらうなど、早めに行動することが大切です。
まとめ 資産管理や終活でお困りなら専門家に相談してみよう
老人ホームには民間施設と公的施設があり、施設ごとに費用も幅があります。ただし、公的施設は人気が高く、確実に入居できるとは限りません。民間施設でも比較的リーズナブルな月額料金で利用できるところもありますが、入居一時金が高額になるケースもあります。老後資金のすべてを入居一時金に回してしまうと、受給する年金額だけでは支払いが厳しくなるかもしれません。有料老人ホームに入居する前に、お金のやりくりに関してはしっかり検討しておきましょう。検討した結果、有料老人ホームに入居できるだけの資産があると分かったものの、「身元引受人がいない」「自分で資産管理できない」「入居時の手配が面倒」「生前整理を手伝ってほしい」など困っていることがあれば、専門家に相談してみるのも一案です。全国シルバーライフ保証協会では、財産管理や任意後見、本人が希望するお葬式などを実行するための手配といった終活サポートも行っています。お気軽に相談ください。
死後事務委任契約施設入居の身元保証
サービス内容がよく分かるパンフレット
無料プレゼント
QRコードをお手持ちのスマートフォン等で
読み取って友だち登録をしてください

友だち追加ボタンをタップして
友だち登録をしてください
【参加無料】終活セミナー
終活に関するセミナー、勉強会、イベントを開催しています