要介護認定区分とは、「介護の必要度に応じて分けられる区分」です。介護保険制度において、介護がどの程度必要かに応じて「要支援1・2」「要介護1〜5」に分類される仕組みになっています。
本記事では、各区分の目安となる状態や利用できるサービスを一覧でまとめた「要介護認定区分の早わかり表」つきで、介護保険制度における要介護認定の全体像を紹介します。
要支援・要介護とは?厚生労働省の定義を紹介
介護保険制度において、身体機能や認知機能に低下が見られる被保険者は、その状態により要支援と要介護のいずれかに区分されます。
厚生労働省による「要支援状態」の定義
「身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(要支援状態区分)のいずれかに該当するものをいう」
要するに、体や心に障害があって、日常生活に少し支障があり、今後の悪化を防ぐためにも部分的な支援が必要な状態ということです。
厚生労働省による「要介護状態」の定義
「身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(要介護状態区分)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう」。
引用:厚生労働省|要介護認定等の概要
要約すると、体や心に障害があるために、日常的な動作をするのに、ずっと介護が必要な状態のことです。要支援よりも重い状態になります。では、要支援と要介護の違いをもう少し詳しく見ていきましょう。
1-1 要支援・要介護の違い
要支援・要介護の認定を受けた方は、介護給付を受けることができます。介護保険では要介護・要支援の状態区分によって1か月の支給限度基準額が決定されます。その限度額の範囲で介護サービスを「現物」給付として受けることができます。要支援と要介護では、それぞれ利用できるサービスが異なります。下表に違いをまとめました。
| 要支援 | 要介護 |
| 状態 | 基本的に自立しているが、日常生活の一部に支援が必要例:入浴や排せつは自力でできるが、浴槽やトイレの掃除などが困難 | 日常生活の多くに介助が必要例:入浴や排せつなどの日常的な動作に介助が必要 |
| 区分 | 要支援1・2 | 要介護1~5 |
| 給付 | 予防給付 | 介護給付 |
| 受けられる介護サービス | 介護予防サービス通所・訪問などが中心。 | 介護サービス幅広い介護サービスが対象。 |
| サービス利用時のケアプランの作成 | 地域包括支援センターが作成 | 担当のケアマネジャーが作成 |
介護保険で受けることができる給付は、要支援の方が対象となる「予防給付」、要介護の方が対象となる「介護給付」に分けられます。
予防給付は、要支援1・2の認定を受けた方を対象に、介護予防サービスや地域密着型介護予防サービスを提供します。介護給付は、要介護1〜5の認定者を対象に、施設サービスや居宅サービス、地域密着型サービスを提供するものです。以下に、それぞれのサービスの種類をまとめました。
予防給付の主なサービス(要支援の方向け)
- 訪問型
・介護予防訪問入浴介護
・介護予防訪問看護
・介護予防訪問リハビリテーション
・介護予防居宅療養管理指導
- 短期入所
・介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
・介護予防短期入所療養介護
- その他
・地域密着型介護予防サービス(認知症対応型通所介護など)
・介護予防支援
・介護予防特定施設入居者生活介護
・介護予防福祉用具貸与
・特定介護予防福祉用具販売
介護給付の主なサービス(要介護の方向け)
- 訪問型
・訪問介護(ホームヘルプサービス)
・訪問入浴介護
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
- 通所型
・通所介護(デイサービス)
・通所リハビリテーション
- 短期入所
・短期入所生活介護(ショートステイ)
・短期入所療養介護
- 施設入所
・特別養護老人ホーム
・介護老人保健施設
・介護医療院
・介護型ケアハウス
- その他
・地域密着型介護サービス(小規模多機能型居宅介護、認知症グループホームなど)
・居宅介護支援
要支援・要介護による違いが分かる!要介護認定区分の早わかり表
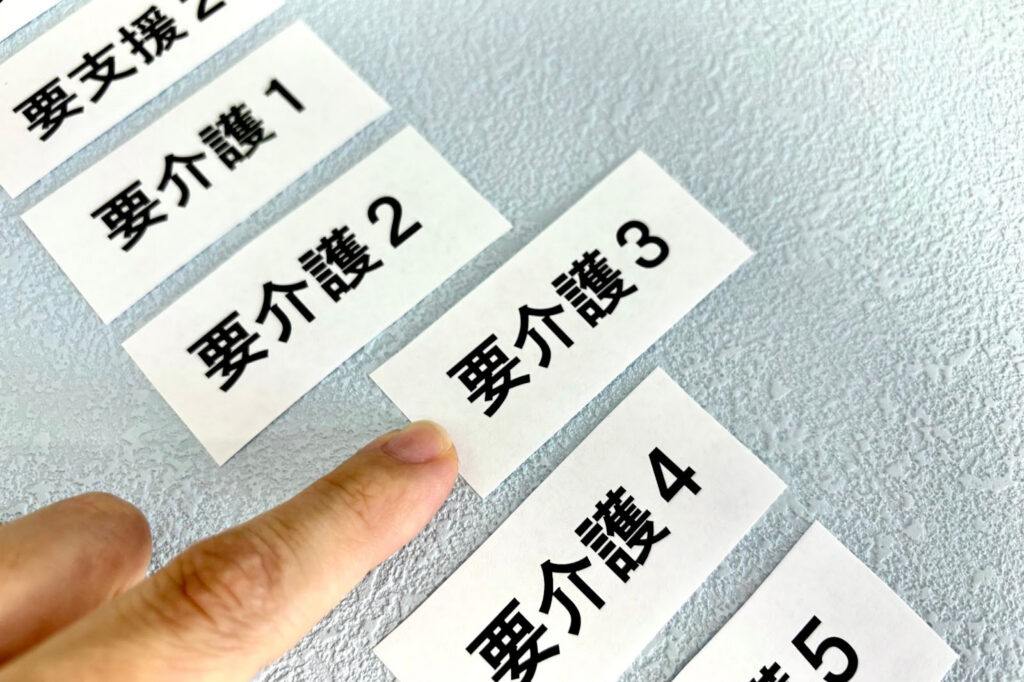
要介護認定では、介護がどの程度必要かを市区町村が判定し、対象者は「非該当(自立)」もしくは「要支援1・2」、「要介護1~5」の7段階の要介護度(介護レベル)に区分されます。
各区分は、認定調査や主治医意見書に基づいて推計される「要介護認定等基準時間」などをもとに決定され、区分ごとに利用できるサービスや支給限度額が異なります。以下の表で、主な違いを確認しましょう。
| 区分 | 認定の目安 | 要介護認定等基準 | 利用できるサービス | 月額の区分支給限度基準額 |
| 非該当(自立) | 一人で日常生活を送れる | 25分未満 | なし | なし |
| 要支援1 | 一部に手助けが必要 | 25分以上32分未満 | 訪問型・通所型・短期入所など | 5万320円 |
| 要支援2 | 起き上がり、立ち上がりが不安定で支援の必要性が高まっている | 32分以上50分未満 | 訪問型・通所型・短期入所など | 10万5,310円 |
| 要介護1 | 要支援2の状態より、身体能力や認知機能の低下がみられる | 32分以上50分未満 | 訪問型・通所型・短期入所・施設入所など | 16万7,650円 |
| 要介護2 | 独力での立ち上がりや歩行が困難で、日常生活の全般に介助が必要 | 50分以上70分未満 | 訪問型・通所型・短期入所・施設入所など | 19万7,050円 |
| 要介護3 | 日常生活の広い範囲で中程度以上の介助が必要(排せつ・入浴など) | 70分以上90分未満 | 訪問型・通所型・短期入所・施設入所など | 27万480円 |
| 要介護4 | ベッドや車いす中心の生活で、日常生活に重度の介助が必要 | 90分以上110分未満 | 訪問型・通所型・短期入所・施設入所など | 30万9,380円 |
| 要介護5 | 常時の全面的な介助が必要。寝たきり状態 | 110分以上 | 訪問型・通所型・短期入所・施設入所など | 36万2,170円 |
※支給限度額は1単位10円換算、自己負担1割の場合の目安額です(2~3割負担の方もいます)。
※「要介護認定等基準時間」とは、認定調査結果に基づいて算出される「1日あたり必要な介護の時間」で、区分判定の参考基準となります。
2-1 要介護認定等基準時間とは?
要介護認定等基準時間とは、介護にかかる手間を時間に換算したもので、認定調査の結果に基づいて算出されます。対象となる介護の分類は、以下の通りです。
| 介護の分類 | 介護の内容 |
| 直接生活介助 | 排泄・入浴・食事などの介護 |
| 間接生活介助 | 洗濯・掃除などの家事支援 |
| 問題行動関連行為 | 徘徊時の捜索、不潔な行為に対する対処など |
| 機能訓練関連行為 | 日常生活訓練や歩行訓練などの機能訓練 |
| 医療関連行為 | 輸血管理やじょくそう(床ずれ)の処置などの診療補助 |
上記の介護に加え、認知症であるかも加味して要介護認定がなされます。
2-2 区分支給限度基準額とは?負担限度額との違い
介護保険サービスには、利用できる上限額の「区分支給限度基準額」が設定されています。これは、要介護認定の区分ごとに、1か月あたりで利用できるサービス費の上限を定めたもので、超過分は全額自己負担になります。限度額は月ごとに適用され、翌月への繰り越しはできません。
利用者の自己負担割合は1〜3割で、所得に応じて変動します(原則は1割負担)。また、サービス費は「単位」で管理されており、基本は1単位あたり10円です。ただし、地域の物価や人件費を反映する趣旨で、地域区分ごとに上乗せ割合が設定されているため、実際の1単位当たりの金額は地域により若干の差があります。
なお、この「区分支給限度基準額」は、厚生労働省が定めた一定のサービスに対して適用されるものであり、すべてのサービスが対象となるものではありません。
以下は対象外とされる主なサービスの例です。
- 居宅療養管理指導
- 特定施設入居者生活介護
- 認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 など
2-2 要支援1の状態と受けられるサービス
要支援1は、日常生活の基本的な動作(食事・排せつ・入浴など)は自立して行えますが、掃除や買い物などにおいて一部支援が必要な状態です。具体的には、起き上がりや歩行時に支えを必要としたり、家事全般に見守りや手助けが求められたりすることがあります。
要支援1に認定された方が利用できる予防給付に該当するサービスは、以下の通りです。
- 訪問型(訪問入浴介護・訪問介護・訪問リハビリテーション など)
- 通所型(介護予防通所リハビリテーション)
- 短期入所型 (ショートステイ・介護予防短期入所療養介護)など
1か月あたりに利用できる区分支給限度基準額は5万320円となっています。
2-3 要支援2の状態と受けられるサービス
要支援2も日常生活を自力で送れますが、片足立ちや日常の意思決定、買い物などを行う能力が低下している状態です。たとえば、入浴中に自分の背中を洗ったり、浴槽を掃除したりすることが難しくなります。
要支援2に認定された方が利用できる予防給付に該当するサービスは、要支援1と同じですが、区分支給限度基準額が10万5,310円と異なります。
2-4 要介護1の状態と受けられるサービス
要支援2と要介護1は、「認知機能の状態」と「状態の安定性」の観点で区分されます。「認知機能の状態」においては、要支援2で認知機能が低下していない場合は、予防給付に該当するサービスを受けることで要介護状態への進行を予防できるとされています。しかし、認知症などで認知機能の低下が見られる場合は要介護1の認定を受ける可能性があります。
「状態の安定性」は、6ヶ月の認定有効期間内に必要な介護の量が変化する可能性で判断するものです。必要な介護量の増加が見込まれる場合は、要介護1を受ける可能性が高くなります。
要介護1は入浴や排せつなどを自分で行えますが、歩行のバランスや思考力に低下が見られる状態です。
要介護1に認定された方が利用できる介護給付に該当するサービスは、以下の通りです。
- 訪問型(ホームヘルプサービス・訪問入浴介護・訪問介護 など)
- 通所型(デイサービス・通所リハビリテーション)
- 短期入所型(ショートステイ・短期入所療養介護)
- 施設入所(介護老人保健施設・介護医療院・介護型ケアハウス)など
要介護1から施設入所が利用できます。
区分支給限度基準額は16万7,650円とされています。
2-5 要介護2の状態と受けられるサービス
要介護2では、立ち上がり・移動・入浴・料理などの日常行為に介助が必要な状態とされます。また、爪切りなどの簡単な日常動作においても介護者による支援が求められる状態です。認知機能の低下により、金銭の管理が難しくなることもあります。
要介護2に認定された方が利用できるサービスも、要介護1の方と同じです。
- 訪問型(ホームヘルプサービス・訪問入浴介護・訪問介護 など)
- 通所型(デイサービス・通所リハビリテーション)
- 短期入所型(ショートステイ・短期入所療養介護)
- 施設入所(介護老人保健施設・介護医療院・介護型ケアハウス)など
要介護2では転倒などの危険性が高まるため、日常生活でより手厚い介護が必要です。外出時の付き添いや、身体介護の比重が高いサービスも増える傾向があります。
区分支給限度基準額は19万7,050円です。
2-6 要介護3の状態と受けられるサービス
要介護3は、身体機能の衰えにより排せつや着替え、寝返りなど日常生活全般において、介護が必要な状態です。認知症の発症など、認知機能の低下もあり、問題行動が見られる場合もあります。継続的な支援が不可欠な方になります。
要介護3に認定された方が利用できるサービスは、以下の通りです。
- 訪問型(ホームヘルプサービス・訪問入浴介護・訪問介護 など)
- 通所型(デイサービス・通所リハビリテーション)
- 短期入所型(ショートステイ・短期入所療養介護)
- 施設入所(介護老人保健施設・介護医療院・介護型ケアハウス・特別養護老人ホーム)など
要介護3からは全面的な介助が必要になるケースが多いことから、特別養護老人ホームへの入所も選択肢に入ります。
区分支給限度基準額は27万480円です。
2-7 要介護4の状態と受けられるサービス
要介護4は、自力で立ったり移動したりすることが難しく、ほとんどの生活動作に介助が必要な状態です。認知症の進行により意思疎通にも困難が見られることがあります。
要介護4に認定された方が利用できるサービスは、以下の通りです。
- 訪問型(ホームヘルプサービス・訪問入浴介護・訪問介護 など)
- 通所型(デイサービス・通所リハビリテーション)
- 短期入所型(ショートステイ・短期入所療養介護)
- 施設入所(介護老人保健施設・介護医療院・介護型ケアハウス・特別養護老人ホーム)など
排せつや清拭、食事の介助が常時必要な状態であり、自宅介護が困難な場合は特別養護老人ホームなどの入所が推奨されます。
また、要介護4の方は、介護保険以外にもおむつ代の助成制度などの各種助成・控除制度を利用できる場合があります。詳細については、お住まいの市区町村に問い合わせましょう。
区分支給限度基準額は30万9,380円です。
2-8 要介護5の状態と受けられるサービス
要介護5は、常時全面的な介助が必要な最重度の状態です。意思疎通が困難な場合が多く、医療面での管理も求められることがあります。
要介護5に認定された方が利用できるサービスは、以下の通りです。
- 訪問型(ホームヘルプサービス・訪問入浴介護・訪問介護 など)
- 通所型(デイサービス・通所リハビリテーション)
- 短期入所型(ショートステイ・短期入所療養介護)
- 施設入所(介護老人保健施設・介護医療院・介護型ケアハウス・特別養護老人ホーム)など
要介護5は、経管栄養、褥瘡(床ずれ)ケア、呼吸管理などの医療的ケアが必要なことも多く、医療職との連携も重要視されます。
区分支給限度基準額は36万2,170円です。
要介護認定区分が決定されるまでの流れ
要介護認定区分は、申請から認定調査、主治医意見書、審査会による判定を経て決定されます。ここではその一連の流れをわかりやすく解説します。
3-1 1|市町村の窓口で要介護認定の申請を行う
要介護認定は、住民票のある市区町村の介護保険担当窓口で申請できます。申請書を持参しての申請のほか、郵送やマイナポータルからのオンライン申請にも対応しています。
【申請できる人】
- 65歳以上の方(第1号被保険者)
- 40歳以上64歳以下で、特定疾病(16種類)により介護が必要とされた方(第2号被保険者)
特定疾病には、がん末期、関節リウマチ、初老期における認知症、脊髄小脳変性症、慢性閉塞性肺疾患などが含まれます。これらの難病に罹ると、若くても介護が必要になるため申請を認められています。
【申請に必要な書類】
- 要介護認定・更新認定申請書
- 介護保険被保険者証
- 医療保険被保険者証(40〜64歳の第2号被保険者のみ)
- 本人確認書類(例:運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 認定調査先(自宅、施設、病院など)の住所や連絡先(認定調査先住所が住民登録地と異なる場合に申請書に記入)
- 委任状(家族や代理人による申請の場合)
※介護が必要な本人の家族は代理で要介護認定の申請が可能です
3-2 2|認定調査を受ける
次は、市区町村が行う調査と審査を受けます。決定までのおおまかな流れは以下の通りです。
- 市区町村の調査員が「認定調査」を行う
- 主治医が意見書を作成する
- コンピューターによる一次判定が行われる(自動推計)
- 介護認定審査会により二次判定(最終決定)が下される
認定調査では、市区町村の認定調査員が自宅や病院を訪問し、心身の状態について74項目を質問・観察します。要介護認定の申請を行った後、申請先の市区町村の担当者から訪問調査を行うための日程確認の連絡がきます。調査は1時間程度が目安で、立ち上がりや歩行などの確認動作も含まれます。
市区町村は、調査結果と主治医意見書の内容を、国が定めたソフトウェアに入力し、1日あたりに必要な介護時間(要介護認定等基準時間)を推計します(一次判定)。その後、医師などの専門家で構成された介護認定審査会が最終的な区分を決定(二次判定)するのが通常の流れです。
3-2-1 要介護認定にかかる期間
要介護認定は原則、申請から30日以内に認定結果が通知されるのが原則ですが、実際には期限内に結果の通知まで至らないケースも多いのが現状です。
認定結果の通知が遅れる背景には、主治医意見書の遅れや人手不足による審査会の滞りなどがあります。こうした課題に対応するため、厚生労働省はデジタル化による処理の効率化や運用の見直しといった、各種改善策の検討を進めています。
3-3 3|要介護認定の決定・認定通知を受ける
要介護認定の結果が確定すると、市区町村から申請者に認定結果通知書が送付されます。結果に納得できない場合は、通知を受け取った日から3か月以内であれば都道府県の介護保険審査会に対して不服申し立てが可能です。
要介護認定には有効期限があり、初回または区分変更申請時の期限は原則6か月(必要と認められる場合は3~12か月に設定可)、2回目以降は原則12か月(必要と認められる場合、更新前と要介護度が異なるときは3~最大36か月、要介護度が同じときは3~最大48か月に設定可)と定められています。
また、認定通知書と併せて「介護保険負担割合証」と「介護保険被保険者証」が届くので、サービス利用時に備えて認定結果通知書と一緒に大切に保管しておきましょう。
要介護認定後に居宅サービス・施設サービスを利用する方法

要介護認定後は、自宅での支援(居宅サービス)や施設での介護(施設サービス)を受けられます。ここでは、各サービスの利用までの流れや手続きについて解説します。
4-1 居宅サービスを利用する
要介護認定を受けた方が訪問介護やデイサービス、ショートステイなどの各種居宅サービスを利用するには、あらかじめ「ケアプラン(介護サービス計画)」を作成する必要があります。
ケアプランとは、本人の心身の状況や生活の希望に応じて、身体機能・認知機能の維持や改善のために「どのようなサービスを、どの頻度で、どの事業者から受けるか」を具体的に記載した計画書です。
このケアプランは、本人または家族が自分で作成することも可能ですが、一般的には「ケアマネジャー(介護支援専門員)」に依頼して作成します。ケアマネジャーは、ケアプランの作成に加え、サービス事業者との調整や必要に応じた計画の見直しも行います。
要介護1〜5に認定された方は、居宅介護支援事業所に依頼して「ケアプラン」を作成します。要支援1・2に認定された方については、地域包括支援センターや委託を受けた居宅介護支援事業者に依頼して「介護予防ケアプラン」を作成します。
4-2 施設サービスを利用する
要介護認定を受けた方で、かつ、自宅での介護が難しい場合は、介護保険の範囲内の施設サービスを選ぶことができます。以下は介護保険の対象となる主な施設です。
- 特別養護老人ホーム(特養)
常時介護が必要な高齢者向け。原則として要介護3以上の方が対象。要介護1または2の方は、やむを得ない事情がある場合に特例的に入所可能。
- 介護老人保健施設(老健)
医療的ケアと在宅復帰支援が目的。リハビリ重視。要介護1以上の方が対象。
- 介護医療院
長期療養が必要な高齢者向けの医療・介護施設。要介護1以上の方が対象。
- 介護付き有料老人ホーム
介護や医療、リハビリなどのサービスを提供する民間施設。「特定施設入所者生活介護」に指定された施設であれば介護保険での入所が可能。要介護1以上の方が対象。
- グループホーム
認知症の方に介護や機能訓練を提供する民間施設。認知症の診断を受けた要支援2、または要介護1以上の方が対象。
入所を希望する場合、まずはケアマネジャーや市区町村の介護保険窓口に相談しましょう。その後、施設の見学などを経て入所の手続きを進めることになります。
なお、施設入所に際しては身元保証人を求められるのが一般的です。身元保証人は緊急時の連絡先や費用未払い時の対応を担います。身元保証人になるのは親族などが一般的ですが、見つからない場合は民間の身元保証サービスなどを活用しましょう。
要介護認定後にレンタル・購入できる福祉用具

介護保険では、施設や在宅サービスだけでなく、福祉用具のレンタルや購入も給付の対象となっています。要介護度に応じて利用できる品目が異なるため、状態に合った用具を選ぶことが重要です。
レンタル対象となる福祉用具の例を紹介します。
要支援1・2、要介護1の方
- 手すり(工事不要のもの)
- スロープ(工事不要のもの)
- 歩行器・歩行補助つえ
- 自動排せつ処理装置(尿のみを自動的に吸引できるもの)
要介護2・3の方(要支援1・2、要介護1に該当する用具以外)
- 車いす
- 車いす付属品(クッション、足置きなど)
- 特殊寝台(電動ベッドなど)
- 特殊寝台付属品(サイドレール、マットレスなど)
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト
要介護4・5の方
上記の全てに加え、自動排せつ処理装置
介護保険で購入できる主な福祉用具(特定福祉用具販売)は以下の通りです。
- 腰掛便座(ポータブルトイレなど)
- 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽手すりなど)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具部分
- 特殊尿器
- 排せつ支援予測機器 など
特定福祉用具については、指定特定福祉用具販売事業者から購入する場合に限り介護保険から費用の支給(7~9割)を受けられます。
要支援・要介護状態になったときに受けられる介護サービスを理解しよう
要支援・要介護の認定を受けると、ケアプランに基づき、訪問介護やデイサービス、ショートステイ、施設入所などの介護サービスを受けられます。身体機能や認知機能の低下を感じている場合は、市区町村の窓口や地域包括支援センターなどに相談してみましょう。
また、介護施設の入居時や入院時には、身元保証人が求められるケースが多く、身寄りがない方にとっては大きなハードルになりかねません。全国シルバーライフ保証協会は、司法書士や行政書士などの士業法人グル-プを母体とした団体です。高齢者のための身元保証サービスや生活支援・死後事務支援などを提供しているので、ぜひお気軽にご相談ください。
死後事務委任契約施設入居の身元保証
サービス内容がよく分かるパンフレット
無料プレゼント
QRコードをお手持ちのスマートフォン等で
読み取って友だち登録をしてください

友だち追加ボタンをタップして
友だち登録をしてください
【参加無料】終活セミナー
終活に関するセミナー、勉強会、イベントを開催しています